
(※イメージ画像)
火災保険を検討しているとき、「免責」という言葉を目にして、どういう意味だろう?と思ったことはありませんか?「免責」とは、保険会社が保険金を支払う責任を免れる(免責される)範囲や金額のことを指します。
「もしものときに保険金がもらえないかもしれない…」と不安に思う方もいるかもしれませんが、この免責の仕組みを正しく理解することで、ご自身に最適な火災保険を選ぶことができます。
この記事では、火災保険における免責の仕組みや、種類ごとの違いをわかりやすく解説します。さらに、免責金額の適切な設定方法や、免責金額を決めるときの注意点についてもご紹介します。この記事を読めば、免責に関する不安が解消され、安心して火災保険に加入できるようになります。
火災保険における「免責」とは?基本の仕組みを解説
火災保険における「免責」とは、保険会社が保険金を支払う義務を免れる範囲や金額のことです。
たとえば、免責金額を5万円に設定していた場合、損害額が5万円以下であれば保険金は支払われず、5万円を超える部分のみが保険金の支払い対象となります。
- 損害額が3万円の場合:免責金額の5万円を下回るため、保険金は0円。
- 損害額が10万円の場合:免責金額5万円を差し引いた、5万円が保険金として支払われる。
このように、免責を設けることで、少額な損害については自己負担となるため、保険会社の事務手続きが簡素化され、その結果、保険料を安くすることができます。
免責には2種類ある?「フランチャイズ方式」と「免責金額方式」
免責の仕組みには、大きく分けて2つの方式があります。現在、多くの保険商品で採用されているのは「免責金額方式」ですが、以前は「フランチャイズ方式」も主流でした。
2-1. フランチャイズ方式
この方式は、損害額が一定の金額(たとえば20万円)を超えた場合、損害額の全額が支払われる仕組みです。
- 損害額が10万円の場合:フランチャイズ金額(20万円)を下回るため、保険金は0円。
- 損害額が30万円の場合:フランチャイズ金額を超えているため、保険金として30万円全額が支払われる。
この方式は、少額な損害には対応できませんが、大きな損害が発生した際には全額補償されるという特徴があります。ただし、現在ではこの方式を採用している保険会社は少なくなっています。
2-2. 免責金額方式(自己負担額方式)
現在主流となっているのがこの方式です。損害額から事前に設定した免責金額(自己負担額)を差し引いた金額が支払われます。
- 免責金額を5万円に設定した場合
- 損害額が3万円の場合:免責金額を下回るため、保険金は0円。
- 損害額が10万円の場合:10万円 − 5万円 = 5万円が支払われる。
この方式は、少額な損害を自己負担することで、保険料を抑えることができるのが大きなメリットです。
「免責金額」を設定するメリット・デメリット
免責金額を設定することは、ご自身の保険料やもしものときの負担額に直結します。そのメリットとデメリットを理解しておきましょう。
メリット
- 保険料が安くなる:免責金額を高く設定するほど、保険会社の支払うリスクが減るため、月々の保険料が安くなります。
- 保険金請求の手間が省ける:少額な損害でいちいち保険会社に連絡する手間が省けます。
デメリット
- 少額な損害は自己負担になる:免責金額以下の損害は、すべて自己負担となります。
- 想定外の出費につながる:自己負担額を高く設定しすぎると、いざというときに大きな出費が必要になる可能性があります。
ご自身の経済状況や、どこまで自己負担できるかをよく考えて設定することが重要です。
免責金額はいくらに設定すべき?選び方のポイント

(※イメージ画像)
免責金額の設定は、ご自身の家計やリスク許容度に合わせて慎重に検討することが大切です。
4-1. 災害の種類によって設定する
火災保険の免責金額は、火災、風災、水災、雪災など、災害の種類ごとに設定できる場合があります。例えば、台風が頻繁に来る地域であれば、風災の免責金額を低く設定するといった対策が可能です。
4-2. 自身の家計状況で決める
緊急時に自己負担できる金額を考えましょう。**「このくらいの修理費用なら、手持ちの貯金で対応できる」**という金額を免責金額に設定するのがおすすめです。
一般的な免責金額は3万円、5万円、10万円が多いですが、中には0円〜100万円以上まで細かく設定できる保険会社もあります。
4-3. 損害のリスクを考える
建物の築年数や構造、立地条件などを考慮して、どんなリスクがあるかを考えます。
- 築年数が古い建物:台風や地震で損害を受けるリスクが高いため、免責金額を低く設定しておくと安心です。
- 河川に近い立地:水災のリスクが高いため、水災の免責金額を低く設定することを検討しましょう。
免責額を設定するときの注意点とよくある疑問
5-1. 免責額は1事故ごとの設定
免責金額は、「1回の事故(災害)ごとに適用される」のが一般的です。年間を通じての合計ではありません。たとえば、台風で1回損害を受けて修理し、その2週間後に別の台風で損害を受けた場合、それぞれに免責金額が適用されます。
5-2. 地震保険の免責
地震保険は、火災保険とは別に加入する保険であり、免責の仕組みも異なります。多くの地震保険では、損害の程度に応じて「全損」「半損」「一部損」などの区分で保険金額が支払われ、自己負担額(免責金額)は設定されていません。
5-3. 災害発生後の保険金請求
損害が発生したら、まずは保険会社に連絡し、被害状況を写真などで記録しておきましょう。そして、保険会社の指示に従って修理の見積もりを取り、必要な書類を提出します。この手続きをスムーズに行うためにも、加入している保険会社の連絡先や、手続きの流れを事前に確認しておくことが大切です。
まとめ
火災保険の「免責」とは、損害が発生した際に契約者が自己負担する金額のことです。この金額を高く設定すると保険料は安くなりますが、少額な損害は全額自己負担となります。
免責の方式は、現在主流の「免責金額方式」と、損害額が一定額を超えた場合に全額補償される「フランチャイズ方式」があります。
ご自身の家計状況や、災害リスクを考慮して、最適な免責金額を設定することが大切です。免責額は1事故ごとに適用される点に注意しましょう。
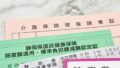

コメント